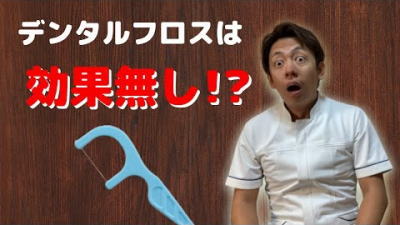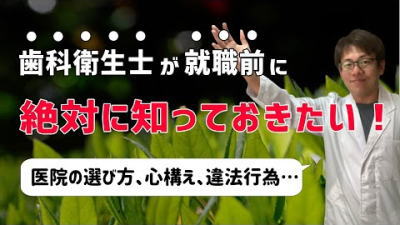根分岐部下の歯周病治療の選択
相談者:
りんご雨さん (68歳:女性)
投稿日時:2025-04-13 11:01:17
質問宜しくお願いいたします。
経過:
1,昨年3月に 40年前以上前に治療した右下奥6.7番が歯冠破折しそうなのでアマルガム除去をし、クラウンを被せるまで仮歯に。
2,治療後6番のみ軽い痛みが出て、アマルガム除去の影響があるのではと、そのまま様子を見て半年程度経過後、痛みがないのでジルコニアクラウンを被せて診療終了。
3,クラウン装着2ヶ月経過後、6番の軽い痛みと右耳や顎の痛みが始まり、クラウンの上から穴を開けて想定外の根幹治療が始まりました。
保険対応で3回ほど根幹治療の処置を受け、3回目の治療で根の分岐部から出血があり、神経を探すことに苦戦していました。
CT撮影を希望しましたが、保険対応では出来ないということでレントゲンのみ3回目の治療時に撮り、大きな問題はないということでした。
4,根幹治療は自費でないと難しいのではないかと思い、治療途中で根幹治療専門医に転院し、レントゲン上で根分岐部に穿孔があり、根は3本、根分岐部の下が既に歯周病になっていて骨も少し下がっていて予後が悪いと言われました。
1回目の治療で 神経は全部抜髄できました。
穿孔部はMTAセメントで修復。
根管治療の先生は 2回目の時に最後の仕上げと仮歯を入れて、3ヶ月・半年と様子を見てクラウンを被せるそうです。
しかし、歯周病の専門医ではないので、根分岐部の歯周病は治療が出来ないそうで、洞窟の様な分岐部に歯間ブラシでケアするしか方法がないそうで、現状維持しか方法がないと言われました。
歯根分割・ブラシが通過できるトンネルには否定的でした。
11月の探針では3,治療時に6になっています。
フロス・歯間ブラシは数十年前から毎日使用しています。
質問
1,歯周病は 根幹治療の様な薬剤治療は出来ないのでしょうか?
2,根分岐部下の歯周病が現状維持の場合、治療が終わった根管に感染等の影響はでないのでしょうか。
また、半年後にクラウンを被せても大丈夫でしょうか。
3,歯周病専門医だと 根分岐部歯周病を治療することができるのでしょうか。
4,歯周病で歯槽骨が溶ける前に 抜歯してインプラントにした方がよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
経過:
1,昨年3月に 40年前以上前に治療した右下奥6.7番が歯冠破折しそうなのでアマルガム除去をし、クラウンを被せるまで仮歯に。
2,治療後6番のみ軽い痛みが出て、アマルガム除去の影響があるのではと、そのまま様子を見て半年程度経過後、痛みがないのでジルコニアクラウンを被せて診療終了。
3,クラウン装着2ヶ月経過後、6番の軽い痛みと右耳や顎の痛みが始まり、クラウンの上から穴を開けて想定外の根幹治療が始まりました。
保険対応で3回ほど根幹治療の処置を受け、3回目の治療で根の分岐部から出血があり、神経を探すことに苦戦していました。
CT撮影を希望しましたが、保険対応では出来ないということでレントゲンのみ3回目の治療時に撮り、大きな問題はないということでした。
4,根幹治療は自費でないと難しいのではないかと思い、治療途中で根幹治療専門医に転院し、レントゲン上で根分岐部に穿孔があり、根は3本、根分岐部の下が既に歯周病になっていて骨も少し下がっていて予後が悪いと言われました。
1回目の治療で 神経は全部抜髄できました。
穿孔部はMTAセメントで修復。
根管治療の先生は 2回目の時に最後の仕上げと仮歯を入れて、3ヶ月・半年と様子を見てクラウンを被せるそうです。
しかし、歯周病の専門医ではないので、根分岐部の歯周病は治療が出来ないそうで、洞窟の様な分岐部に歯間ブラシでケアするしか方法がないそうで、現状維持しか方法がないと言われました。
歯根分割・ブラシが通過できるトンネルには否定的でした。
11月の探針では3,治療時に6になっています。
フロス・歯間ブラシは数十年前から毎日使用しています。
質問
1,歯周病は 根幹治療の様な薬剤治療は出来ないのでしょうか?
2,根分岐部下の歯周病が現状維持の場合、治療が終わった根管に感染等の影響はでないのでしょうか。
また、半年後にクラウンを被せても大丈夫でしょうか。
3,歯周病専門医だと 根分岐部歯周病を治療することができるのでしょうか。
4,歯周病で歯槽骨が溶ける前に 抜歯してインプラントにした方がよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
 回答1
回答1 回答2
回答2船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2025-04-14 12:28:49
こんにちは。
根分岐部は加齢や治療歴により問題を生じやすい部位になると思います。
歯科医の治療方針によっては、分割して連結するという選択もあるでしょうし、天然歯の構造のメリットを使ってそのまま穿孔を閉鎖して使用するという方針もあると思います。
歯の内部からの崩壊を防ぐためには感染が進んでいく歯質はすっかり取り切って人工物に置換しておく治療になり、これが歯内療法になります。
歯周治療は歯の外側の問題を解決する方法で多くのケースで歯の外側に細菌や歯石などの生体に対して害になる物がくっついているのを取り除きお手入れしやすくしておく治療になりますね。
>1
薬と言いますと、再生療法が保険適用可能になっていて最近はリグロスがありますね。
自費になると幅が広がるかもしれません。
>2
厳密にいえば象牙質の構造は象牙細管という構造になっていますから外側(歯の外周)から感染が進みますが、MTAセメントは細菌が繁殖しないアルカリ性の薬剤ですからそこに隣接した部位からは隣接しない部分よりも悪くなっていくのは遅いのではないかと思います。
とはいえ、細菌が常に繁殖して酸性になり続ける時間が長ければ長いほど歯のミネラル分が溶けていき一般によく表現される虫歯状態になると思いますから、うまく清掃しておくか定期的にメンテナンスでバイオフィルムを綺麗に取り除いてもらっておくほうが良いと思います。
>3
歯周病専門医に限定されなくとも一般の開業医でも根分岐部病は非常に多い病態のため、うまく良い状態をコントロールし続けてくれる歯科医院は多いと思います。
専門医でなければ入れる事ができない機械などはありませんし、雇えない医療スタッフという縛りもありませんから、根分岐部病変にもうまく対応してくれる歯科医院に出会えれば良いのだと思いますね。
とはいえ、わかりにくいでしょうからとりあえず歯周病専門医に相談されるのが良いのでしょう。
>4
ご自身の歯をいかに大切に使って行きたいかの熱量によって選択は変わるのではないかと思います。
もちろん問題が生じたら抜歯してインプラントにしてしまうという選択は悪くはないと思います。
そういう選択を許容されるならば骨や歯周組織の条件が悪くならないできるだけ早期に抜歯してインプラント治療に進まれる方が良いでしょう。
根分岐部は加齢や治療歴により問題を生じやすい部位になると思います。
歯科医の治療方針によっては、分割して連結するという選択もあるでしょうし、天然歯の構造のメリットを使ってそのまま穿孔を閉鎖して使用するという方針もあると思います。
歯の内部からの崩壊を防ぐためには感染が進んでいく歯質はすっかり取り切って人工物に置換しておく治療になり、これが歯内療法になります。
歯周治療は歯の外側の問題を解決する方法で多くのケースで歯の外側に細菌や歯石などの生体に対して害になる物がくっついているのを取り除きお手入れしやすくしておく治療になりますね。
>1
薬と言いますと、再生療法が保険適用可能になっていて最近はリグロスがありますね。
自費になると幅が広がるかもしれません。
>2
厳密にいえば象牙質の構造は象牙細管という構造になっていますから外側(歯の外周)から感染が進みますが、MTAセメントは細菌が繁殖しないアルカリ性の薬剤ですからそこに隣接した部位からは隣接しない部分よりも悪くなっていくのは遅いのではないかと思います。
とはいえ、細菌が常に繁殖して酸性になり続ける時間が長ければ長いほど歯のミネラル分が溶けていき一般によく表現される虫歯状態になると思いますから、うまく清掃しておくか定期的にメンテナンスでバイオフィルムを綺麗に取り除いてもらっておくほうが良いと思います。
>3
歯周病専門医に限定されなくとも一般の開業医でも根分岐部病は非常に多い病態のため、うまく良い状態をコントロールし続けてくれる歯科医院は多いと思います。
専門医でなければ入れる事ができない機械などはありませんし、雇えない医療スタッフという縛りもありませんから、根分岐部病変にもうまく対応してくれる歯科医院に出会えれば良いのだと思いますね。
とはいえ、わかりにくいでしょうからとりあえず歯周病専門医に相談されるのが良いのでしょう。
>4
ご自身の歯をいかに大切に使って行きたいかの熱量によって選択は変わるのではないかと思います。
もちろん問題が生じたら抜歯してインプラントにしてしまうという選択は悪くはないと思います。
そういう選択を許容されるならば骨や歯周組織の条件が悪くならないできるだけ早期に抜歯してインプラント治療に進まれる方が良いでしょう。
 相談者からの返信
相談者からの返信相談者:
りんご雨さん
返信日時:2025-04-15 12:14:17
 回答3
回答3船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2025-04-15 12:34:10
骨粗鬆症の診断が下り、投薬が始まりますと、インプラント治療は行ってもらえなくなるか服薬を一時的にやめられるか整形や内科との連携が必要になってくるのではないかと思います。
>1
歯周病は歯がなければない病気ですから、抜歯すれば歯周病ではなく抜歯窩の治癒という事になります。
抜歯により大きく組織を失う事にならないようにインプラント治療を前提とした処置が追加されることもありますから、インプラントを行う歯科医に抜歯をしてもらうか連携をとるようになると思います。
とはいえ、まだ根分岐部病変になって経過が短く歯に動揺もないという事でしたら通常抜歯だけで終わるかもしれません。
インプラントの即時埋入法などもありますし、おかかりの歯科医にご相談ください。
>2
先に回答したように歯周病は歯の周囲の病気ですから問題がある歯を抜けば歯周病はなくなりますし、何らかの病巣があればそれは別病名になります。
とはいえ、通常、歯周病で抜歯を行う際にきちんと病巣は掻爬されるのが一般的ですからご心配不要と思います。
>1
歯周病は歯がなければない病気ですから、抜歯すれば歯周病ではなく抜歯窩の治癒という事になります。
抜歯により大きく組織を失う事にならないようにインプラント治療を前提とした処置が追加されることもありますから、インプラントを行う歯科医に抜歯をしてもらうか連携をとるようになると思います。
とはいえ、まだ根分岐部病変になって経過が短く歯に動揺もないという事でしたら通常抜歯だけで終わるかもしれません。
インプラントの即時埋入法などもありますし、おかかりの歯科医にご相談ください。
>2
先に回答したように歯周病は歯の周囲の病気ですから問題がある歯を抜けば歯周病はなくなりますし、何らかの病巣があればそれは別病名になります。
とはいえ、通常、歯周病で抜歯を行う際にきちんと病巣は掻爬されるのが一般的ですからご心配不要と思います。
 相談者からの返信
相談者からの返信相談者:
りんご雨さん
返信日時:2025-04-16 18:03:25
ふなちゃん先生
詳しい説明ありがとうございました。
とても分かりやすい説明で、今後の道が見えたように思います。
また、宜しくお願いします。
詳しい説明ありがとうございました。
とても分かりやすい説明で、今後の道が見えたように思います。
また、宜しくお願いします。
| タイトル | 根分岐部下の歯周病治療の選択 |
|---|---|
| 質問者 | りんご雨さん |
| 地域 | 非公開 |
| 年齢 | 68歳 |
| 性別 | 女性 |
| 職業 | 非公開 |
| カテゴリ |
インプラント治療法 歯周病(歯槽膿漏)治療 歯周病その他 根分岐部病変 |
| 回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。