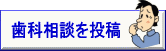 |
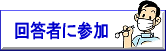 |
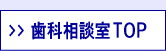 |
|||
|
|
| ⇒歯科相談掲示板TOPに戻る |
この記事へコメントを投稿、投稿した記事を編集・削除する際にはログインが必要です
|
| ⇒歯科相談掲示板TOPに戻る |
|
|
| copyright©2006- 歯医者/歯科情報の歯チャンネル All Rights Reserved. |
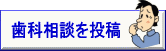 |
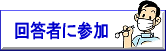 |
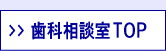 |
|||
|
|
| ⇒歯科相談掲示板TOPに戻る |
この記事へコメントを投稿、投稿した記事を編集・削除する際にはログインが必要です
|
| ⇒歯科相談掲示板TOPに戻る |
|
|
| copyright©2006- 歯医者/歯科情報の歯チャンネル All Rights Reserved. |